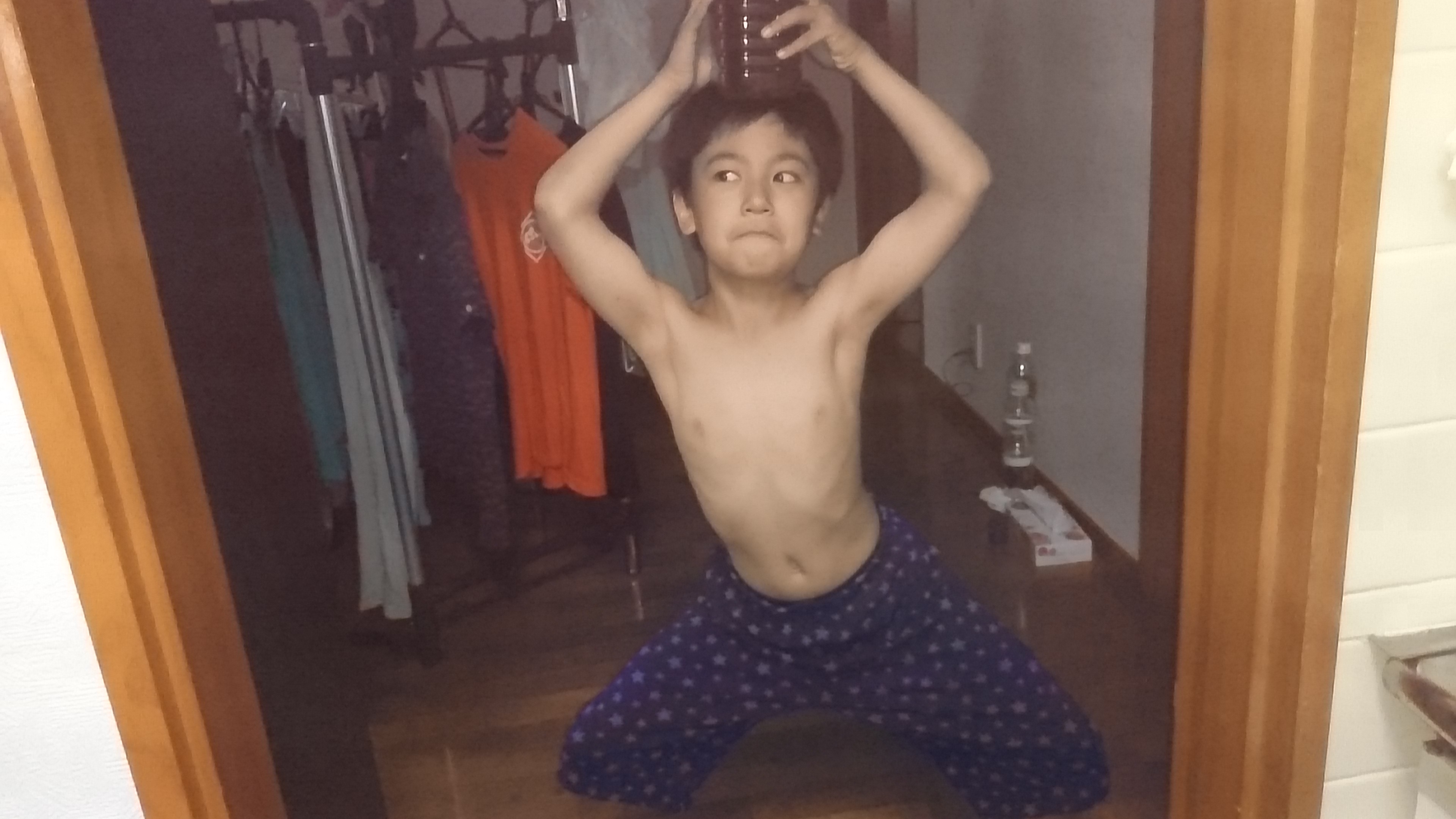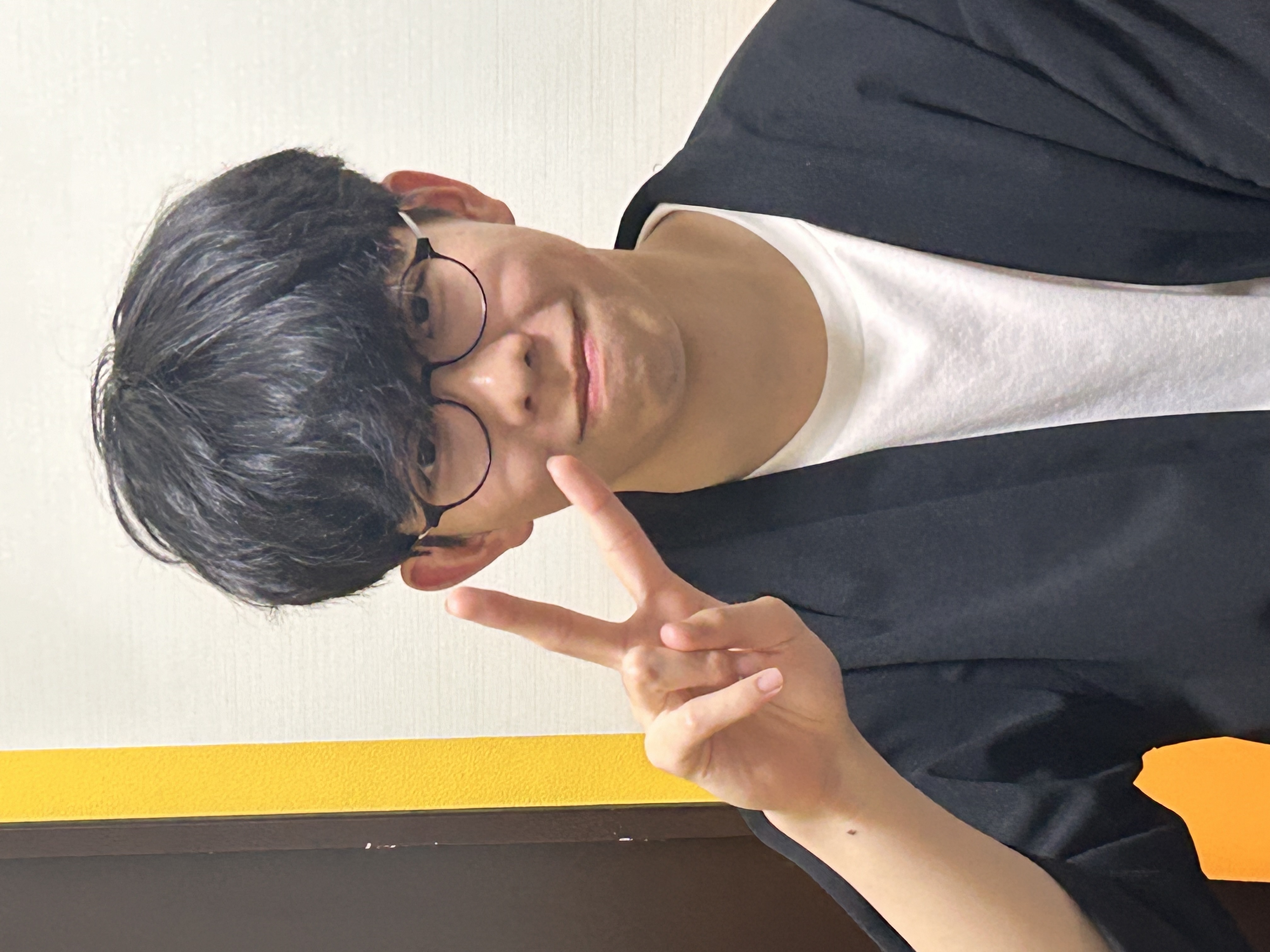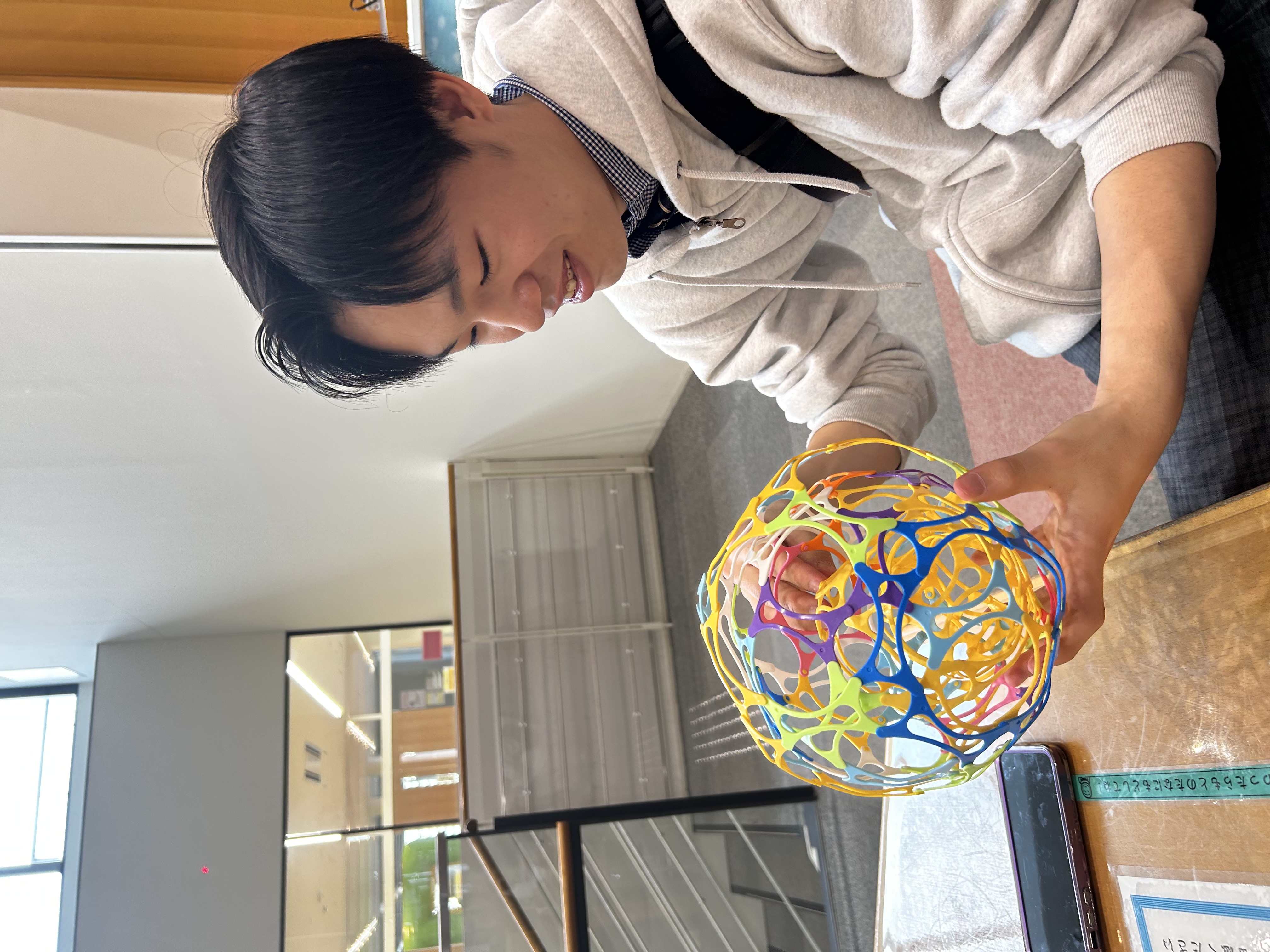サイトに入って、どうぞ
午前7時16分。
窓の外は、半端に凍ったアスファルトと、まだ眠そうな空気の粒で満ちている。
白んだ空にカラスの黒だけがやけに濃く浮かんで、まるで世界がモノクロームを選んだみたいだ。
秋田の冬は、感情の出力装置としては少々性能が良すぎる。
感傷も、諦観も、憂鬱も、全部過剰になる。
…それでも、制服のポケットに手を突っ込んで登校する僕は、たぶん今日も「高校生」なんだと思う。
駅前のロータリー、誰も乗らないバス、点滅する信号、ビニール傘の骨が折れた音。
一つひとつが、世界の裏側を覗かせるトリガーに見えてくる。
たとえばこの信号が一度も青にならなかったら、
誰かにちゃんと愛された記憶なんてものは、本当は最初から存在していなかったんじゃないか、って。
くだらない仮定。でも、高校生の“文学”ってだいたいそういうものだろう?
君の名前を、今でも思い出す。
いや、正確には、「名前を思い出すという行為」が、僕の中で宗教化してる。
あれはたぶん秋の終わり、空が妙に高くて、遠かった。
君は「この空、たぶん地球のじゃないよ」って言って、
僕は「地球の所有権なんてとっくに誰かに奪われてる」って返した。
そのやりとりすら、もう実在しないんじゃないかと思う夜がある。
哲学書の序文みたいなことを言うけどさ、
「存在」は証明されることで初めて現実になる。
じゃあ、君が僕の夢に出てくるたびに泣く理由は?
なぜ僕は、校舎の3階から見える夕暮れを、あれほど鮮明に嫌えるのか?
その理由に名前をつけるとしたら、きっと「思い出の亡霊(ゴースト・オブ・ユア・メモリー)」だ。
恋という言葉を使いたくない。
あまりにも凡庸だから。
けれど、「君と向かい合ったときだけ、世界の重力が違っていた」
という感覚を、他にどう表現すればいい?
教室には、くだらない正義と、うすら寒い笑い声が充満してる。
社会科教師の言葉は、たぶん音波という形式を借りた無音。
「人生とは~」なんて語りだした瞬間、すべての言葉が薄っぺらに聞こえるのは、
僕が思春期の真っただ中にいるからじゃなくて、
世界がとっくに死語で構成されてるからだ。
廊下で水たまりを避けながら歩くとき、ふと君のことを思い出す。
なぜって、君は雨の中を傘なしで歩くくせに、風邪ひいたことがなかったから。
「私は濡れてるんじゃなくて、空に触ってるだけ」って言ってた君の台詞、
正直今ならちょっと笑える。でも、少しだけ、うらやましかった。
家に帰って、カーテンを閉めて、ノートを開く。
そこには何も書かれていない。いや、「まだ」書かれていない。
空白には、想像力よりも真実が詰まってる。
文字は過去を記録するけど、空白は未来を許容する。
僕が書こうとしたのは詩じゃない。怪文書でもない。
ただ、君がもうこの世界のどこにもいないかもしれないという現実を、
僕がうまく咀嚼できずにいる、という記録。
時計の針は、いつも通り。
だけど今日だけは、進んでるのか戻ってるのかわからない。
部屋の空気が、昨日と微妙に違う気がする。
たぶんそれは、「君がもう現れない確率」が、昨日より少しだけ上がったからだ。
明日も学校に行く。
哲学書と数学のノートを一緒に鞄に詰めて。
すました顔で、世界の崩壊を他人事みたいに観察してやる。
僕は高校生だ。
この世で一番、無敵で、脆くて、そして――文学的な存在だ。
著作・ChatGPT.